「僧帽筋」って聞いたことありますか?
背中の上の方にある大きな筋肉です.
「僧帽(そうぼう)」の由来は,ヨーロッパの修道士がかぶっていた フード付きの頭巾(ケープのような形) を指しているといわれています.
起始・停止・作用をざっくり整理
起始(どこから始まる?)
・後頭骨(外後頭隆起)
・項靭帯
・第7頚椎,第1〜12胸椎の棘突起
停止(どこにつく?)
・鎖骨外側1/3
・肩峰
・肩甲棘
作用(どう働く?)
上部線維:肩甲骨の挙上
中部線維:肩甲骨の内転
下部線維:肩甲骨の下制
日常生活でのイメージ
・肩をすくめる(肩甲骨の挙上)
・姿勢を正すように胸をはる(肩甲骨の内転+下制)
僧帽筋のストレッチで肩こりは改善する?
僧帽筋は首の後ろから背中にかけて存在する筋肉であることから,よく肩こりに関与していると言われています.
「デスクワークで生じた肩こりには僧帽筋のストレッチが効果的」これはよく目にしますが,本当にそうなのでしょうか.みんなで「肩こりの改善にストレッチが有効であるか」を考えてみましょう!
まずはデスクの前に座りパソコンを開いて,キーボードで文字を入力してみましょう.このとき,肩甲骨は外転しているはずです.
つまり,僧帽筋の中部線維は肩甲骨を内転の作用を持っているため,ストレッチを行うよりも筋肉の収縮が必要となるのです.
しかし,肩こり改善=僧帽筋のストレッチは間違っているかといわれると,そうでもありません.
デスクワーク時は肩に力が入っていたり,デスクの高さが高すぎたりしている場合があります.このときは肩甲骨が挙上し,僧帽筋の上部線維は過緊張の状態になっているのです.
つまり,肩甲骨を挙上させる作用を持つ僧帽筋の上部線維には,ストレッチをして伸ばす必要があるのです.
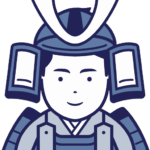
デスクワーク後には僧帽筋上部線維はストレッチ,中部線維や下部線維には収縮を促すことが大事なんだね!
※ここまでの解説は顎をしっかり引いて首が前に出ていない状態での姿勢について考えています.ストレートネックと言われるような姿勢ではもう少し別のことも考えなければならないのでご注意を!(首が出ている姿勢では僧帽筋の上部線維が過緊張ではなく伸張されている場合があるので,ストレッチよりも収縮を促したほうが良い可能性があります)
まとめ
・僧帽筋は「上部・中部・下部」で働きが異なる
・デスクワーク中は肩甲骨が外転しやすく,中部・下部線維は収縮不足になりやすい
・肩に力が入ると上部線維が過緊張となりやすい
・姿勢タイプ(デスクの高さや首の位置など)によってアプローチが変わるので,自分の姿勢を確認することが大切!


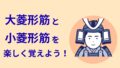
コメント